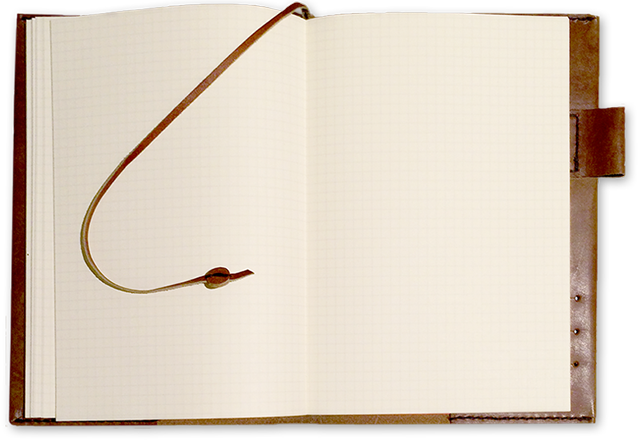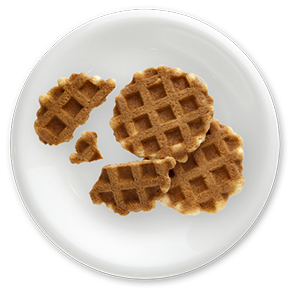ソフィア・コッポラ監督の映画「マリーアントワネット」を観て、原作のほうにも興味がでたので読んでみました。原作はこちら。
再度申し上げますが、私のフランス革命の知識は「ベルばら」レベルでしかありません。マリー・アントワネットがらみの小説は、他に遠藤周作氏の著書を読んだことがありますが、もう随分前なのと、「う?ん、あまり好きじゃない」くらいの感想しかもてませんでした。
映画の「マリー・アントワネット」は、映画を観た時の日記にも書きましたが(その日記はこちら♪)、歴史大河というのではなく、マリーというオーストリアの皇室に生まれた少女が、フランスの王家に嫁に行き、どんな風に異種な環境と折り合っていったか、どんな風に暮らしたか、どんなものを愛したか、そんな暮らし方をキレイにPOPに描いた、といった映画であります。
この映画は賛否両論ありますが、ワタシ的には説明的なコトも説教臭い所も一切なく、マリーの日常を淡々と追い続け、革命の嵐をポン!と最後に持ってきたところが、かえってこの人たちがなんでこの後滅んでいったのかを、リアルに感じさせてくれたような気がして、なかなかおもしろいと思ったのでした。
こんな映画の原作はさて、どんなマリー・アントワネットなんだろう?
はじめその本を書店で手に取った時は、正直その厚さ&上・下巻というのに購入をためらったのですが(^_^;)、中を開くとふんだんに肖像画などのカラーの写真が載せられていて、また、文中の脚注もそのページごとに入っていて、海外翻訳モノに慣れてない私のような読者にも、読みやすいように親切に作られてるなぁって思いました。
で、内容ですが、これは「小説」的な脚色が一切ありません。この辺あの映画の原作としてなるほどなぁって思いました。
小説というよりは、伝記に近いかな?残された公式文書をはじめ、当時の貴族たちの日記や手紙からマリー・アントワネットという人物の取った行動、話した言葉、また彼女を取り巻く周りの人物の行動などを淡々と書き出してっています。
彼女の誕生時のヨーロッパの政治状況、少女時代の教育のされ方、賢母といわれるマリア・テレジアのほかの姉妹への偏愛、上の姉が急逝した為、準備不足のまま「繰り上がり当選」のような形でフランスとの政略結婚の駒にされていたこと。
フランス王太子妃となったわずか14歳の彼女は、まずその為の教育をほとんど受けていなかった。彼女の責任は世継ぎを生んでフランスとオーストリアの友好関係をさらに固めること、宮廷内で親オーストリアのネットワークを築き、祖国に利益をもたらす事・・・だけど世継ぎは肝心のルイ16世がその気になってくれなくて全く望めず、政治的にも準備不足な彼女は大使としての役割はほとんど出来ず、かえってフランス王家内の派閥抗争?にいいように利用されてしまう始末・・・。
15人兄妹の末娘の彼女にとって、女帝・マリア・テレジアは母というよりは畏怖するべく大きな存在であり、その母の期待に応えられない自分、世継ぎを産まなくてはいけないのに全く協力の気配すらない夫・・・←マリーのいろんな努力や一喜一憂した様子が手紙などに残っていてちょっと泣ける(つД`)
映画同様、小説的脚色はなく、淡々とその状況が今も残る資料から書き出されていきます。
そのうち国王が崩御し、若すぎる2人は国王・王妃になってしまいます。
政治が苦手で優柔不断でややオタクな国王と、同じく政治が苦手でやや軽薄な王妃、王家の財政は前国王が妾に使っちゃっててすでに破綻寸前、だけどいっこうに以前の華やかな暮らしを続けて当然と思ってる人たちばかりの宮廷・・・歴史を知ってる私が見ると「こりゃダメだ」ともう思うしかないんだけど・・・本人達に気づくすべもなく・・・。
この本を読んで思ったのは、たぶん、王も王妃も基本的に善良な人だったんだと思う。ただ不幸なことはその「職業」にあまりにも適性がなかったのと、自分で選べなかったこと。でもマリーはフランスに嫁に来て、帰りたいとも言わず(実際は言ったかも知れないけど)、その環境(運命)を受け入れ、自分なりに適応していこうとしている。
子供が出来てからは今までの享楽的なところは消え、家庭的な優しい母となり、夫や子供をはじめ、義妹や周りの人に対しても、とても愛情の深い人でした。最期の裁判の時には息子に対してのでっち上げの醜聞に毅然と戦う、強き母でもありました。
「パンがなかったらお菓子を食べればいいのに」
このセリフはマリー・アントワネットが言ったとされているけど、実際彼女が言ったセリフではないそうです。でも随分長くマリーが言ったと信じられていました。
時代は革命へと移っていき、華やかなベルサイユでの生活は突如として幕を引きました(映画でも突如でしたね)。その後あちこちに移されたり、逃亡を試みたりするけど失敗してしまい(このあたりのいろんなエピソードを見ても、王族とその周りの人の勘の悪さというか、嗅覚の無さ?みたいなのが感じられてならない)、
外国人の彼女は「オーストリア女」といわれ続け、たくさんの悪名を背負わされました。そしてまず国王が、その後、王妃の彼女も革命の名のもとに生贄<スケープゴート>になって、断頭台に登ったのです。
この辺のくだりが恐い。
たとえばランバル公妃。マリー・アントワネットの親友として最期まで外国に逃げず、行動を共にしていた彼女は、民衆の手にかかり虐殺されてしまいます。しかもその後、遺体はバラバラに切り刻まれ、その首は槍に刺され、わざわざマリーの牢獄の窓から見えるように掲げれたとか・・・。
革命の名のもとにというよりも、ただ血を見たい、ただ殺戮をしたい、そんな『野蛮』が誰にも止められない・・・いったいフランス革命で死んだ人は何人になるんだろう?そのうち正式な裁判を受けられた人は何人だったんだろう??
なんとなく中国の文化大革命を思い出させます。これも『さらばわが愛-覇王別姫』という映画や、テレビドラマの『大地の子』でリアルに知った歴史ですが。
定期的に巻き起こる・・・この殺戮の嵐みたいなのって。。。マリーの時代は18世紀の終わりでもう中世ではないし、まして中国での話はまだ30年くらいしか経ってないのだ。もちろんカンボジアでもアフリカでも最近までに起こったことだ。一度火がついてしまったらもう誰にも消せない、全て燃やしてしまうまで消せない・・・人間の歴史として、恐く感じないではいられないですね・・・。
ルイ16世もマリーも、なんて運の悪い人だろう。いろんな巡り会わせが全て悪い方に向かって、もちろん本人達の王と王妃としての資質に問題はあれど、歴代の王にはもっととんでもない人なんてたくさんいたであろうし、本人の過失だけであんな無残な最期が与えられたとは思えないので・・・。
ただもう『運』とか『めぐり合わせ』とかに対して絶対に勝てないことへの恐さを思い知らされます。
映画を観た時も思ったんだけど、彼女達のベルサイユでの生活は、地面から10?くらい浮いているようなまさしく『バブル』な暮らしだった。その中でしか通用しない言葉、価値観、小さな優劣、しきたり、そんなものが彼女達の世界の全てになっていた。
そして、気がつくと足元から崩れてしまった。
前兆は必ずあったはずだ。ただ気がつけなかったし、気がついてもどうしていいのかわからなかった。
これって、今の私たちの暮らしにも当てはまるんじゃないかな?
自分の身近な家庭でも職場でもコミュニティでも、その『組織』がなんとなく10cmほど浮き上がって感じることは無いだろうか?『東京』は日本の中で浮き上がってはないだろうか?はたまた『日本』は世界の中で浮き上がってないだろうか?
・・・時々そんな風に考えてみることもいいのかもしれないですね。
王妃が最期に暮らした牢獄で、王妃の身の回りを親身になってお世話していたのがロザリー・ラモリエールという若い女だったそうです。おお!ロザリー!!・・・と、ベルばら読者の私は嬉しくなったのでした♪


 横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。
横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。