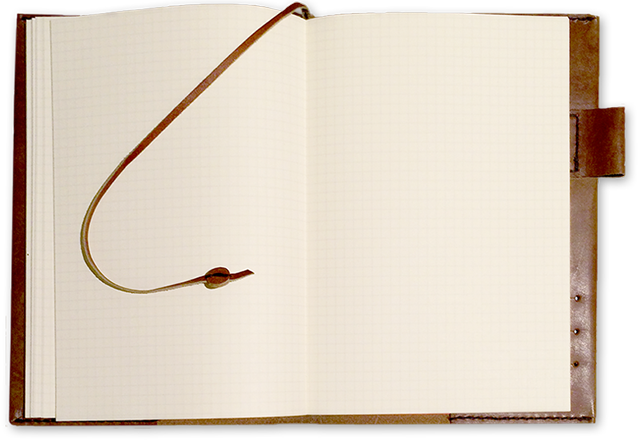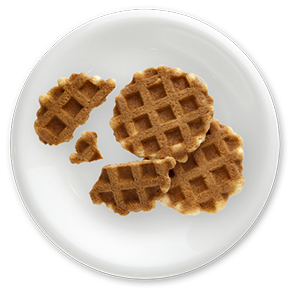10月最後の週末はあちこちでハロウィンイベントが開かれていて、仮装した人たちの写真がSNSにアップされているのを多く見ました。
すっかり季節の風物詩として日本にも定着したハロウィン。オレンジと黒・紫のハロウィンカラーはインパクトもあり可愛く、クリスマスとはまた違うウキウキ感があります。
私が初めて「ハロウィン」なるイベントを知ったのは映画の「E.T」だった。夜、仮装した子どもたちがE.Tを連れて外にいく。自転車で夜空を飛ぶ有名なシーンは確かその夜じゃなかったかな?
当時中学生の私は「ハロウィン」を知らなかったので、なんだろう?アメリカのお祭りみたいなものかな?と思ってました。そういえば家の古いアルバムの中に町内会の盆踊りで仮装大会やったときの写真があって母がインド人の恰好をしていた(笑)あんなやつかなと。
そしてもう一度ハロウィンに出会ったのが、名作「風と共に去りぬ」の続編として出版された長編小説「スカーレット」だった。
それは、E.Tの中での楽しそうなハロウィンとはまるで違い、もっと昔、イギリス併合時代のアイルランドの迷信深い人々にとってのハロウィンで、それまでハロウィンは子どものお祭りイベントだと思っていた私にはすごく驚きで印象的だった。
風と共に去りぬの続編「スカーレット」とは
本編は世界中で超有名な歴史小説であり映画でもあるので詳しい説明は不要だと思うけど、ざっくり説明すると南北戦争時代のアメリカ南部に生まれたスカーレット・オハラという美貌の女性の半生を描いた作品です。

大名作映画・風と共に去りぬのドラマチックなポスター
風と共に去りぬ : 場面カット – 映画.com より画像引用
1936年の初出版後、空前の大ベストセラーとなったにもかかわらず、作者のマーガレット・ミッチェルはどんなに熱望されても「この作品はこれで完結」として続編を書かないまま、1949年に交通事故で亡くなった。
その後ミッチェルの相続人たちが、将来著作権が切れた時に三流作家に勝手に続編を書かれてしまうことを懸念し、先手を打って続編の出版を企画し執筆者を募集した。そこで選ばれたのがアレクサンドラ・リプリーという女性作家で、彼女が書き上げたのが「スカーレット」だ。
ファンの期待の中、1991年に出版され大ベストセラーとなり、瞬く間に世界中で翻訳されテレビドラマ化もされた。日本でも小説家の森瑤子氏が翻訳し1992年に新潮社から発売されました。
しかしあれだけの超有名大作・名作の続編ということで話題は集めたけれど、作品としての評価はあまり高くはなく、日本の森瑤子訳本も今は絶版となっていて入手が困難な状態になっています。
※なのでこの先内容をネタバレで書きますので、展開を知りたくない人はご注意ください。
続編は、タラに戻ったスカーレットがマミーの死を看取るところから始まる。メラニーに続きスカーレットは自分を愛してくれた人間をまたも失ってしまうのだ。
孤独な彼女はなんとしてもレットの愛を取り戻そうと、彼の実家があるチャールストンに行く。しかしレットは徹底して彼女から逃げ続ける。ここまでレットが自分を遠ざけたがるのは「まだ自分を愛してるからだ」という、スカーレットのポジティブな思い上がりはアシュレイを追いかけていた昔のままでちっとも成長していない。
チャールストンは上流階級の人の多く住むアメリカ南部の最も古い街だ。スカーレットの亡くなった母・エレンの実家もここにある。
フランス系の名門の家に生まれるも初恋に破れた母エレンは、その後アイルランド移民で「格下の成り上がり者」だった親子ほど年の違う父ジェラルドと結婚した。
チャールストンの社交界に一応は上品に迎えられるスカーレットだけど、結局はこの町の「いけず」文化(←敗戦で傷ついてるからさらに厄介な)に馴染めず、レットは彼女を遠ざけ続け復縁は叶わなかった。
しかしここでアイルランド人の父方の従兄弟コラム・オハラ神父に出会い、父の生まれた国を見てみたいという好奇心もありその後彼女はアイルランドに渡るのだ。
当時のアイルランドはイギリスの支配下にあり、多くのアイルランド人が土地を奪われていたがオハラ家一族は健在で、スカーレットは100歳になる祖母、老ケティ・スカーレット・オハラの誕生日を祝うことができた。
そこでスカーレットは自分が妊娠していることに気がつく。
じつはチャールストンで、これが最後でもうあなたを追うことはしないと約束し、スカーレットはレットのヨットに乗せてもらっていた。しかし洋上で天候が変わり遭難してしまう。奇跡的に浜に打ち上げられ命が助かった二人は、その時に暖を取った漁師小屋で結ばれてしまうのだ(しかしレットはその後、生きていた喜びで発情しただけだと冷たく言い放つ)
妊娠したことで「これでレットを取り戻せる」と強気になった彼女は(ほんと成長してない)、もう少しアイルランドを見たいからと帰る予定の船を遅らせてしまう。そしてその後、レットが再婚したという新聞記事を見ることになるのだ。
ケルトの因習が残るアイルランドのハロウィンとは…
失意のスカーレットはアイルランドで子どもを産み育てていくことを決める。
なんせ彼女は金持ちのアメリカ人。その気になればどこに行っても暮らせるのだ。オハラ家の人々は彼女に同情し優しく迎えてくれる。
スカーレットは、イギリス人に土地を奪われ没落したアイルランドのオハラ家再興の為に土地を買い戻したいと考え、持ち前の行動力ですぐに実行する。
アイルランドの人々は(とりわけオハラ一族は)、女のくせに事業をやるなんてけしからん!なんてことはいわない。むしろ彼女は憎きイギリス人から土地を取り戻した「英雄」になったのだ。しかし誇り高く、施しを受けるを善としないオハラ一族は、彼女が買い戻した土地には住んでくれなかった。
女領主となったスカーレットはオハラ一族を代表する存在となり、周りの人々から「ザ・オハラ」と呼ばれるようになった。
この時代のアイルランドの政治情勢の描写、こうと決めた時のスカーレットの行動力、オハラ一族の誇り高さと頑固さとスカーレットの善意が通じない悲しさ、この辺の展開はすごくおもしろい。登場人物もかなり多くなるんだけどそれぞれがすごくよく描けていると思う。
ある嵐の夜、スカーレットは新しく建設した領主館でついに出産を迎えるのだけど、難産で出血がひどく母子ともに命が危なくなった時、得体のしれない風体の老女が突然現れ、彼女のおなかを刃物でさばいて赤ちゃんを取り上げる。今でいう帝王切開?
彼女は森の古い塔に住む、賢女グラーニャ。そしてもうひとつの呼ばれ名は「魔女カイリャハ」
土地を取り戻したアメリカ人の女領主・スカーレットに対しての感謝の思いでやってきたのだという。しかし自分は魔女と呼ばれていることも知ってるので、悪い噂が立つことを心配し森へ帰っていく。
しかしこれがハロウィンの夜の出来事で、嵐の夜に森から魔女が現れ血まみれの部屋の中で悪魔の子を取り上げた、という噂は瞬く間に静かに領内に広がっていくのだ。
当時のアイルランドの人たちは、古いケルトの神話や迷信と共に生きている。毎晩妖精のために牛乳の入ったボウルを戸口に置く、森の道を通るときは妖精がぶつからないよう「シャフェン」と言う、ブラシで髪が絡まるのは意地悪な妖精プーカのしわざ、といったように。

これはゴブリン
ケルト神話というと、昔のゲームブックやRPGなどでもよくモチーフになっていて、レプラコーン、ブリギット、プーカ、パンシーなど、名前を聞くだけで不思議な世界に誘われるようなファンタジックさと、少しおどろおどろしい感じのイメージがありますね。
けっこう前だけど、当時勤めていた会社の研修でイギリスのウェールズに行ったことがあります。
カーディフという町から車で3時間、ウェールズの風景はひたすら羊・羊・羊(笑)
崖の上に古城のような建物が見えたり、古い教会の前にはたくさんの墓石が立っていたりで、夜になったら吸血鬼が出てくるといわれても違和感のない風景ばかりでした。

宿泊したのはウェールズにあるLlangoed Hall(ランゴイド・ホール)
泊まったホテルも一部が16世紀?の建物ということで、朝もやがかかった早朝の風景は神秘的で、小さな妖精たちが草花の隅にいてもおかしくないような独特の「風土」を感じました。ウェールズはアイルランドと同じケルト国でもあるんですよね。
「スカーレット」の中で描かれている、アイルランドの風景描写はとても綿密で印象的です。

ホテル内のお部屋。素敵だけど場所によっては「出る」という噂もw
さてしかし、物語の時代では、霊界とこの世とが交差するハロウィンの嵐の夜に生まれたこの子は「悪魔との取り換え子」と呼ばれてしまうのだ。この生まれはのちのち、彼女がこの土地で生きていけない理由になっていきます。
アイルランドで生きていくスカーレットの成長
アメリカ人で、さらに元々ファンタジーな想像力が全くないスカーレットにとって、「バカバカしい」としか思えないことだけど、生まれた娘「キャット」に危害が加えられることだけは我慢できない。しかし自分はすでに「ザ・オハラ」という立場であり、ここでの仕事がたくさんある。
土地を所有するということは、その土地に縛りつけられることだったのだ。それは愛とよく似ていた。
スカーレットの領地「バリハラ」には、彼女の良き理解者である従兄弟のコラム神父が連れてきた人間が多く集まり。それぞれの暮らしを作りはじめている。
しかし実は、コラム神父は反イギリス政府運動の指導者で、彼が連れてくる人々はみなそのレジスタンスのメンバーだったのだ。アメリカ人が領主のバリハラは彼らが政府に警戒されずに集まれて、銃器を隠すことができる絶好の町だった。
スカーレットは何も知らない。コラム神父はスカーレットを大切な従姉妹としてとても愛していたけれど、彼の野心はそれとは別にきっちりと分けられていた。
コラム神父との信頼関係は、スカーレットと隣の土地の領主、フェントン伯爵との縁談が持ち上がった時に揺らぎ始める。
スカーレットは変わらずレットを愛していたけれど、レットは再婚し妻が妊娠中と聞いた。だからもうどうにもならないのだ。自分には愛する娘キャットがいる。この子がいれば生きていける。
スカーレットはキャットを生んではじめて「我が子への盲目的・絶対的な愛」を知る(これまでにも3人生んでいるけど)。そしてそれと同時に、敬愛してやまなかった亡き母に対しての「もしかして母は誰も愛してなかったのでは?母は幸福ではなかったのでは?」という恐ろしい考えを打ち消せなくなっていく。
お母さまはあたしを愛して下さった。それは確か、でも、あたしがキャットを今愛するようにではない。そうよ、これも確かだわ。あたしを無条件に愛しては下さらなかった。あたしがあたしらしくしていると、いつも悲しそうになさった。そして本来とは違うあたしを演じると、褒めて下さった。母は、あたしに、あたしでない人間になることを望んでいた。とても優しいやり方だったが、それは同時に絶対的な強さを持ってもいた。(略)
お母さまは失敗なさったのだ。あたしたちの育て方を間違ったのだ。
その考えは、スカーレットを深くたじろがせた。今日という日まで、母エレンは彼女の神ともいうべき絶対的な存在、完璧さの象徴だった。
母はどこでどう間違ったのだろうか?スカーレットは懸命に考えた。母としてではなく、一人の女としてみようとした。すると答えが透けてみえた。
母は幸せではなかった!これが答えだわ。しかしそれは決していい気分にはさせなかった。その発見は、彼女のこれまでの人生観を覆すほどの恐ろしい力をもっていた。(略)
エレンは誰彼となく、娘たちであろうと、夫のジェラルドであろうと黒人たちであろうと、へだてなく愛していた。それはつまり、誰に対しても距離があったということではないだろうか?母の愛は冷ややかだった。そう言って悪ければ、愛情深くはなかった。キャットに対するスカーレットほど盲目的ではなかった。なぜだろう?
なぜなら、エレンの中には火が燃えていなかったからだ。エレンの命の火、愛の火はすでに消えていた。(略)
あんなに慈悲深かった女性が、一人の女としては幸せでなかったなんて…。自分自身が幸せでない女性が、どうして回りのものに幸せを与えられるだろう?自分にないものを与えることなどできないのだ。
ここではじめて、スカーレットは「成長」していくんですよね。完璧な「善」として絶対的な存在だった母に疑いを持ち始めたときから。
そんな頃、アメリカとの往復の船の中や、ダブリンの競馬場などでレットの姿をよく見るようになる。どうも商売や付き合いで彼もアイルランドに来ることが多くなっているようだ。しかしスカーレットはレットをまだ愛していても、かつてのような執着心はもう消えている。
フェントン伯爵との結婚も、領地が倍になること、父親のいないキャットが「伯爵令嬢」になれることなどのメリットを考えてのことだった。しかしコラム神父はそれを許すことができない。フェントン伯爵は自分たちにとって「搾取する側の人間=敵」だからだ。
コラム神父はついにスカーレットに、バリハラの住民が実はみな反政府運動の同志であり、教会の地下にはすでにたくさんの銃器が隠されていることを打ち明ける。
愕然とするスカーレット。自分がこれまで大切に育ててきた土地が、町が、キャットの故郷が、彼らの活動次第では火の海になってしまうかもしれないのだ。
きな臭くなる政治事情、コラム神父の裏切りと暴走、エスカレートしていく村人からのキャットへのいじめ、生まれながらの大貴族であるフェントン伯爵の本性…そしてついに火の手が上がるバリハラ。
物語はクライマックスに向かっていき、そして最後の最後に現れるのは!
やはり!レット・バトラーなんですよ!
まさに命がけだった森瑤子さんの「超訳」
というわけで、最終的にスカーレットとレット・バトラーがその後どうなるの?についての答えは「ハッピーエンド」であります。
しかしこのレットが登場する場面が本当に最後の最後で、しかもそれまでレットの心理描写がほとんど無いのでやっぱり置いてきぼり感はいなめない内容だと思う。
でも、ではこの長編小説は駄作なのか?と言われたら、絶対にそんなことはないです。ここまでの中でかなりワクワクしたり涙を流したり、スカーレットの心の成長にホッとしたり(笑)しましたから。
これはきっと、翻訳した森瑤子さんの力が大きかったと思います。作品本編の熱烈なファンであった森さんは、原作者リプリーがインタビューで「私はどちらかというと、スカーレットのような女性は好きではない」と言ってるのを目にしてしまい、「冗談じゃない!」と思わず大声で叫んだそうです。
作家が自分の書く主人公を愛さなかったら、どうして読者の共感を得るつもりなのだろう?第一、主人公を愛せないで、作家は小説が書けるものだろうか?
森さんは居ても立ってもいられなくなり、スカーレットの翻訳権を取ったばかりの新潮社に電話し、ぜひ自分に翻訳をさせてくれと頼み込んだらしい。
しかし翻訳をしながら苦労したのが、ヒロイン・スカーレットの視点だけで書かれてることでどうしても平坦な物語になってしまう点。レット・バトラー側の心理やドラマが書き込まれてないのが不満だけど自分が勝手に書き足すわけにも行かない。
森さんは悩みながらも「風と共に去りぬ」の続編なのだから本編作者のミッチェルならどうするだろうか?という軸で、翻訳上のさまざまな問題を解決したそうだ。
私は、作家としての良心から、止むに止まれず翻訳の範囲を広げることがあったが、同様に作家としての良心から、翻訳の節度を守ることに腐心した。この二つの相反する作業こそが、この仕事の最も苦しく困難な部分であったのだ。
翻訳に関してのこの姿勢は、私の作家生命をかけなければならない性質のものかもしれない。異訳、超訳、その他の言葉をそれに与える人もいるだろう。私に言えることは、こういう型が、私にとっての唯一の良心的な翻訳であったということである。
(略)
私は巫女でいい。言葉の巫女。願わくば、あの「風と共に去りぬ」の偉大な作家マーガレット・ミッチェルの巫女であれたら---。
この文章には最後に1992年10月6日と日付が入っていて、森瑤子さんは翌年の1993年7月6日に亡くなっている。
命がけでこの作品を翻訳されたんだろうと改めて思う。
ハロウィンになると私はいつもこの森瑤子さんの訳した「スカーレット」を思い出すけれど、これがいま絶版になっていることがひどく残念でならない。
私はどこが森さんの「超訳」なのかはわからないけれど、ところどころ確かに「これは森さんかな?」と感じる文章はあった。先に紹介した母は幸せではなかった?のあたりとか(これは私の勝手な憶測)
あとラストのところもかなり書き足してると聞く(これは本当らしい)。最後のところでレットがやってきた理由が「キャットの存在」を知ったからか、そうではなかったか、が。
原作では「知らなかった」ままレットがやって来て、森さん訳は「知ったから」来た、になっているらしい。
私は原本を読んでいない(英語だし)のでわからない。しかしそう聞くと「知らなかった」のほうが納まりが良いような気がしてしまう。森さんがなぜそこを変えたのかは謎である。
それでもこの森さん訳の「スカーレット」はまだまだ発売しててほしいと強く思うのです。
そして、偉大な原作の続編というのはどんなに名作であってもこき下ろされるのが宿命のように思える。今あらためて読むとやっぱりおもしろいですよ!
どこに行っても結局その社会の中で「異分子」になってしまうスカーレットは、同じく生まれながらの異分子であるレット・バトラーとともに、広い広い海に出て2人の王国を見つけるのが一番似合っている。
「イエス!バトラー船長!」
で終わる森瑤子さんの「スカーレット」がいつか復刊される日を願いつつ、待てない方はぜひ図書館か古本屋で探してみてくださいね。
参考リンク
- へこたれない女。<風と共に去りぬ> | Rucca*Lusikka
ちょうど10年前に自分で書いていた「風と共に去りぬ」本編についての感想記事です
紹介した本と映画はこちら
マーケットプライスには出ていますね。本編の方は去年新しい訳でも出されてるようです。でも大久保&竹内訳は本当に素晴らしいのでどうでしょう?
津雲 むつみさんのコミックもかなり完成度の高い素晴らしい内容です。


 横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。
横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。