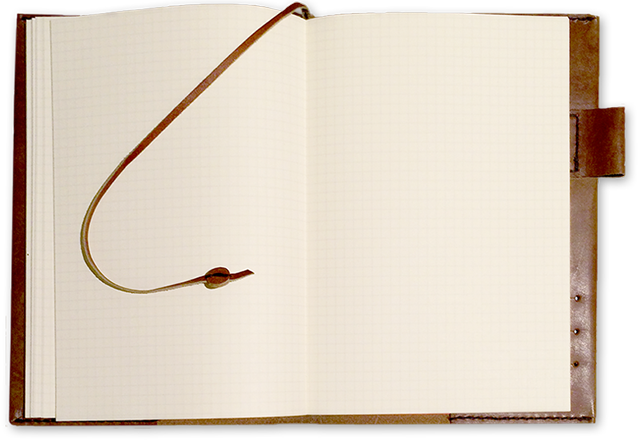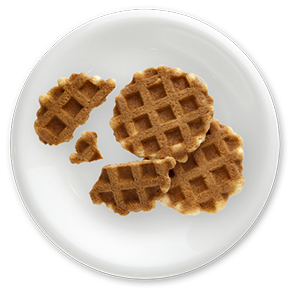六の宮の姫君という短編小説があります。作者は芥川龍之介。
けっこう前に読んだのですが、ちょっと思い出すことがあって改めて探してみたけど本はもう持っていませんでした。でもネットで調べたら青空文庫にありました。
どんなお話なのかを簡単に説明いたしますね。
六の宮の姫君:あらすじ
時代はおそらく平安時代、京の六の宮の近くに、そこそこの身分の夫婦と娘が住んでいます。両親は娘を昔かたぎに大切に育ててきたけれど、娘が年頃になる頃相次いで亡くなってしまいます。
お姫様育ちの娘には家計の采配なんて出来ません。たちまち生活に困り、屋敷のいろんな調度品を売りながら乳母が必死に娘の世話をしますが、日に日に使用人たちも暇を取るようになります。
困窮した生活に、乳母は姫に結婚を勧めます。姫は本意でないけれど生活のため仕方なく承諾して、その後男が通ってくるようになります。(当時は通い婚ですがこの場合娘は正式な妻になったということにはなりません)
男はなかなかいい人で姫にも優しく、生活も援助してくれ暮らしも安定しました。でも姫は男を頼もしく思いながらも、別に好きでも嫌いでもなかった。姫にとっての幸せは両親が生きていた頃のような安心した生活なのです。
ところが男が遠地に長く赴任することになってしまった。5年経てば戻れるよといって男は行ってしまい姫はまたひとりになってしまった。男は任地で結婚してしまい(この時代はよくあること)、5年経っても戻ってこなかった。
男からの仕送りは途絶え生活はまたも困窮し、乳母はもう殿は戻ってこないから、と、姫に新しい男を紹介しますが、姫は「わたしはもう何も入らぬ。生きようとも死なうとも一つ事ぢや。……」といって断ります。

9年後、京に再び帰った男は、ふと姫を思い出し家を訪ねるけどそこは荒れ果てた廃屋になっていました。心配になった男は姫の行方を捜します。
雨宿りした朱雀門の近くで、病人らしい女と年老いた尼がいるのを見つけました。やせ枯れたその女は姫でした。男は姫を抱きかかえるも、姫はもう臨終の間際で、尼(姫の乳母)はその場にいた乞食法師に姫に経を読んでくれと頼みます。
法師は姫を往生させる為に念仏を唱えよというけれど、姫は
「何も、――何も見えませぬ。暗い中に風ばかり、――冷たい風ばかり吹いて参りまする。」
と、うわごとをいうばかりでそのまま死んでしまいました。
その後、朱雀門で女の泣き声がする、といううわさを聞き、ある侍がためしに行ってみると、確かに女のすすり泣く声が聞こえます。侍が刀を抜こうとすると、そこにあの法師が出てきてこういいました。
「あれは極楽も地獄も知らぬ、腑甲斐ない女の魂でござる。御仏を念じておやりなされ。」
・・・と、そんなお話です。
極楽も地獄も知らぬ=ふがいない女
それだけの話なんだけどね。この話が比喩するものは何なのかな?ってちょっと考えてみたのです。
たとえばこのお姫様は『極楽も地獄も知らぬふがいない女』とされています。どんな人生だったかというと読んでのとおり、周りのお膳立ての中でしか生きられない、なすがまま、流されるまま、です。
お姫様には、両親がなくなった後、乳母や使用人の為に私が何とかしなくては!という選択肢はありませんでした。ただ両親が生きてた頃の暮らしがしたいだけ。
この時代の女が経済的基盤を持つのには、『男』に通わせるほか選択肢がないという不条理もあるけど、だったらそれはそれで、たとえば最初の男にもっと尽くして遠地にいっても自分を忘れないようにさせる努力をするとか、いっそ自分もついていくとか、やれることはいっぱいあったはずだ!!
尽くしてくれた乳母の為に、進んで再婚してもよかったはずだ!!
この姫は最期まで、自分の為に、誰かの為に、生きる努力や戦いをしなかった。
極楽も地獄も知らない=ふがいない女
ふがいない、か。自分の人生を生きて来なかったということだろうか。だから成仏できなかったと。
と、私は思ったわけですが、いかがでしょうか?
こういう余韻を楽しめるから短編小説ってけっこう好きですね。
参考図書
青空文庫:六の宮の姫君 芥川龍之介


 横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。
横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。